機関投資家動向
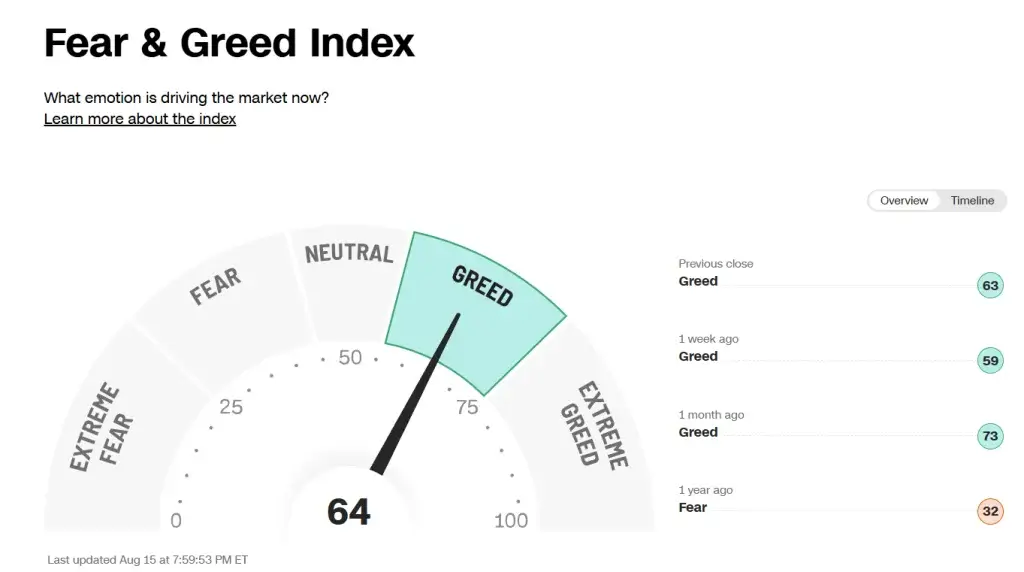
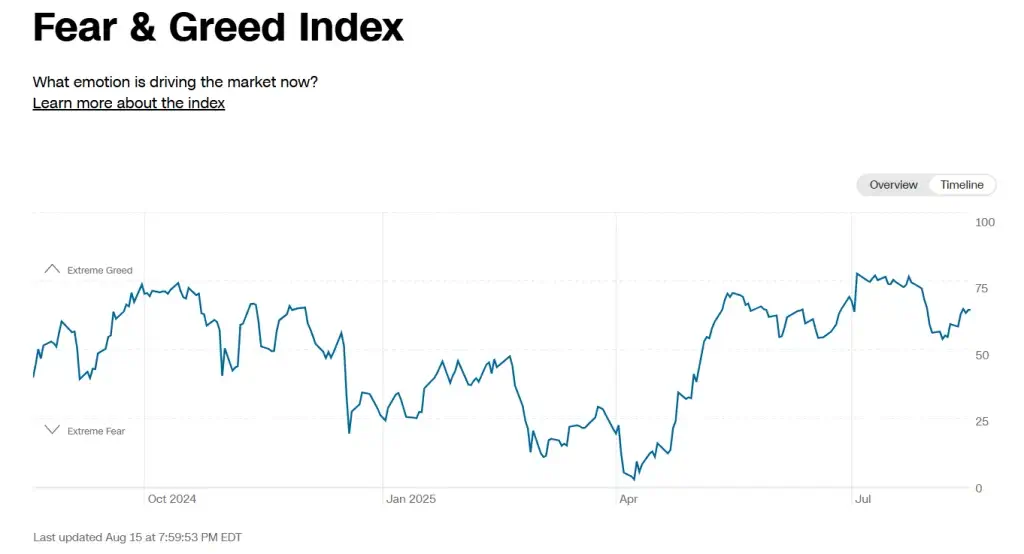



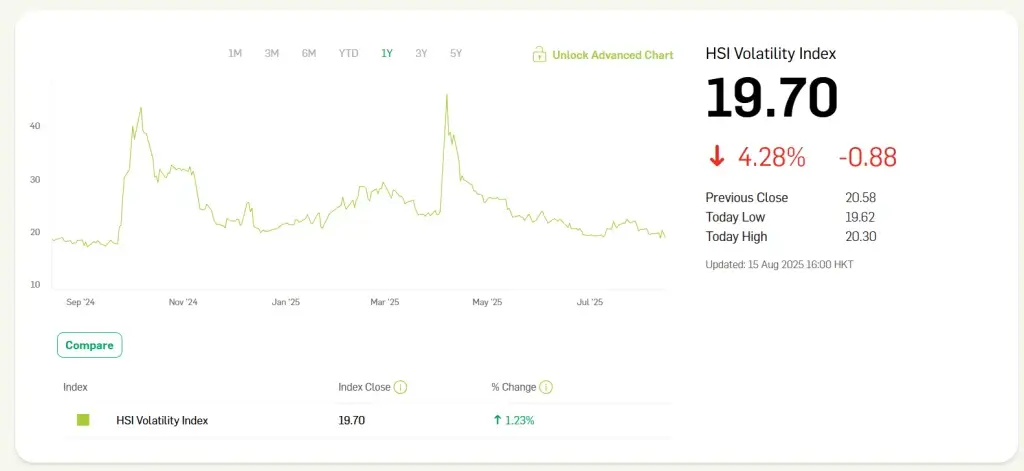

世界の富裕層1%と億万長者を顧客とするトラベルコンサルタント会社シエナ・チャールズのジャクリン・シエナ・インディア最高経営責任者(CEO)は「典型的な高級リゾートから離れ、より高いプライバシー性と排他性を備えた目的地を求める傾向が強まっている」と話す。
例えば、イタリアのコモ湖ではなくオルタ湖、フランスのカンヌではなくコルシカ島、ギリシャのミコノス島ではなくパトモス島、スペインのマヨルカ島ではなくメノルカ島といった具合だ。
カリブ海ではサン・バルテルミー島のような著名なスポットではなく、コモ・パロット・ケイやジャンビー・ベイ・アイランドといったプライベートアイランド型リゾートが選ばれている。

ヘッジファンドは石油株を売り、太陽光関連株のショートポジションを縮小させている。過去4年間にわたり支配的だったエネルギー関連株の投資戦略を転換しつつある様子だ。
トライベカ・インベストメント・パートナーズのポートフォリオマネジャー、トッド・ウォーレン氏は「一部のクリーンエネルギー関連銘柄に底打ちの兆し」が見られると述べ、それが起きたのは「石油市場で需給バランスに対する一定の懸念が生じた時期と重なる」と指摘した。
インベスコ・ソーラー上場投資信託(ETF)構成銘柄を平均で売り越しとしているヘッジファンドの割合は、6月に3%に低下した。これは環境関連銘柄が過去最高値付近にあった21年4月以来の低水準。また、ファースト・トラスト・グローバル・ウインド・エナジーETFの構成銘柄を買い越しとしているファンドの数は、2月に2年半ぶりの多さだった。6月に買い越しの数は減ったものの、依然として買い越しが売り越しを大きく上回った。
一部のヘッジファンド運用者は、人工知能(AI)がエネルギー需要の急増を引き起こし、再生可能エネルギーにとって新たな追い風になるとの見方を示している。
ロンドンを拠点とするセルウッド・アセット・マネジメントの株式担当CIO、カリム・ムサレム氏は「AIが人生で目にする最大の出来事になるだろうと、市場は伝えている」と指摘。AIによるエネルギー需要を満たすには再生可能エネルギーが大きな役割を果たす必要があり、「最も早く市場に供給できるから」だと説明した。

利益追求型アルゴリズムよりもAIモデルの構築に魅力を感じて転身を図るクオンツ人材は多くの場合、金融業界に匹敵する好待遇が約束される。しかし、転職後の実務が期待外れに終わるリスクも抱えている。
「誘い文句は『われわれと一緒に究極のAIをつくろう』というものだ」と語るのは、かつてジェーン・ストリートでトレーダーを務め、現在はシステマティックトレーディング系スタートアップに在籍するアグスティン・レブロン氏だ。「しかし実際には、多くの人が『広告で人々にモノを買わせる方法を考える仕事』に行き着くのではないかと感じている」と続けた。
ハイテク分野の人材採用を手がけるマイク・ドゥーナン氏は「過去12-18カ月で、クオンツの経歴を持つ人材を求めるAI企業やソフトウエア企業からの求人が40-50%程度増加した」と話す。
クオンツ系の金融企業が、競合他社に転職した元社員を訴えるケースは時折見られる。しかし、金融機関と直接競合しないAI企業への転職では、訴訟に発展する可能性は低い。多くの大手AI企業が拠点を構えるカリフォルニア州では、競業避止契約の締結が原則として禁止されている。
ハドソン・リバー・トレーディングでAI部門を統括するイアン・ダニング氏は5月、以下の内容をXに投稿した。「オープンAIやアンスロピックなどで研究者として働いていて、過剰な採用や組織の混乱、採用基準の低下に嫌気が差していませんか? ニューヨークに移りたくありませんか? 何か違うことをしたくないですか? メールでもダイレクトメッセージでも、絵はがきでも構いません。ご連絡ください」

抹茶専門店「マッチャフル(Matchaful)」は抹茶ラテの容量を4分の1減らすことで原材料費を抑え、店頭価格を据え置いている。同カフェを複数店舗経営する創業者のハンナ・ヘイブス氏は、卸売や電子商取引(EC)の顧客向けには価格を最大30%引き上げる方針をすでに固めている。
マッチャフルの主要供給元である静岡県の会社、流通サービスを経営する服部吉明氏は、近年の高気温などが供給難に拍車をかけていると述べた。同氏の農園では昨年の収穫量が約25%減少。総生産量の最大7倍に達する注文が寄せられ、価格を引き上げたという。



ドゥ氏らは最近、対ドルでのユーロ買いをトレーダーに推奨。ユーロ・ドルは年末までに約3%上昇し、1ユーロ=1.20ドル前後になると見込んでいる。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は8月に入り約1.3%低下。年初来では約8%安と、17年以来最悪のパフォーマンスとなっている。

米ゴールドマン・サックス・グループは、イジー・イングランダー氏率いるミレニアム・マネジメントへの出資持ち分を、100万ドルから最大2000万ドルまでの範囲で顧客に売り出している。同行の関係資料で明らかになった。
運用資産780億ドル超を抱えるミレニアムは約140億ドルの企業評価額で10-15%の持ち分を取得する投資家を募っている。上限の15%が売却された場合、20億ドルの資金調達となる。そのうち約半分はゴールドマンのピーターズヒル部門から、残りはミレニアム自体が政府系ファンド(SWF)などの大手機関投資家に打診する形となる。
関係資料によると、ピーターズヒルは調達資金を特別目的会社(SPV)に投入する。出資者には1%の運用報酬と10%の成功報酬(キャリー)を徴収する。ミレニアムに直接出資する機関投資家には、こうした追加手数料は課されない。
ミレニアムの安定的なリターン実績は、投資家を引きつける可能性がある。同社のヘッジファンドは1990年以降、損失を出したのは2008年の1度だけで3.5%のマイナスリターンだった。それ以外の年は、9年間を除いて10%以上のリターンを上げてきた。さらに、投資資金には5年間のロックアップ期間が設けられており、急な資金流出のリスクは限定されている。

AI部門を再編し、約50人で構成する「メタ・ スーパーインテリジェンス・ラボ」(MSL)は、スケールAIでCEOを務めたアレクサンドル・ワン氏、マイクロソフト傘下のソフトウエア開発プラットフォーム、米ギットハブのCEO経験者ナット・フリードマン氏が率いている。
ハーバードビジネススクールで20年以上チームダイナミクスを研究してきたボリス・グロイスバーグ教授は「ウォール街やシリコンバレーには、最も有能な人材を集めれば魔法のような成果が出てくるという考え方がある。実際には魔法のようなことは起きず、嫉妬や陰口、妨害行為がまん延する場合が多い」と指摘する。
2011年にグロイスバーグ氏らが公表した研究報告は、ウォール街の主要金融会社のリサーチチームで「スター」アナリストが一定数を超えるとパフォーマンスが損なわれると結論付けた。組織マネジメントの研究者メレディス・ベルビン氏は1970年代の段階で、全員が高いIQを持つチームは議論が長くなりがちで、協調性に乏しく意思決定が難航すると分析していた。

人工知能(AI)スタートアップのコヒアは14日、新たな資金調達ラウンドで5億ドル(約740億円)を調達したと発表した。企業や政府向けにAIサービスを販売し、大手テック企業との競争に挑む取り組みの一環だ。


スーパーエイジャーの重要な特徴の一つは、非常に社交的な雰囲気の人々だということだ。人とのつながりを大切にし、地域社会で活躍しているケースが多い。この点は興味深い。孤立は認知症発症のリスク因子であり、社会的に活発で居続けることが予防につながると判明しているからだ。
どのスーパーエイジャーにも共通するもう一つの特徴は、自律性や自由、独立性の感覚だ。彼らは自分で意思決定して、望み通りの生活を送っている。
ただ、健康的な行動という点に関しては、スーパーエイジャーにもあらゆるタイプが存在する。我々が研究するスーパーエイジャーの中には、心臓病や糖尿病を抱える人、積極的に運動しない人、同年代と変わらない食生活を送っている人もいる。
がいるわけではないので、98歳ではなく108歳まで生きられたかどうかは、何とも言えない。
CNN:あなたの興味深い発見の多くは、脳組織を提供したスーパーエイジャーの研究から得られたものです。スーパーエイジャーの脳の記憶中枢に関してどんなことが分かっているのでしょうか?
ゲフェン氏:我々の研究では、注意や動機づけ、認知的エンゲージメントを担う脳の部位、いわゆる「帯状皮質」がスーパーエイジャーでは厚いことが示されている。50〜60代の人と比べても分厚かった。
脳の記憶中枢である海馬を調べたところ、スーパーエイジャーは「普通の」同年代と比べ、タウたんぱく質のもつれが3分の1しかないことも分かった。タウたんぱく質の異常形成はアルツハイマー病の重要な兆候の一つだ。
アルツハイマー病では、日常生活で注意力を維持する役割を担う「コリン作動系」の1次ニューロンも、タウの標的になる。しかし、スーパーエイジャーの脳ではそれが起きない。つまり、スーパーエイジャーのコリン作動系はより強靱(きょうじん)だとみられ、また理由は分からないものの、可塑(かそ)性や柔軟性も高いようだ。
この点は興味深い。私が見るところ、スーパーエイジャーは集中力が高いからだ。彼らは注意深く、熱心に耳を傾けることができる。そうでもなければ、ランダムな単語15個のうち13個を30分後に思い出したりできないはず。まるで鑿(のみ)で皮質に単語を刻み込んでいるようだ。
スーパーエイジャーの脳はまた、嗅内(きゅうない)皮質の細胞がより大きく、健康的な点も特徴だ。嗅内皮質は記憶と学習に不可欠な領域で、海馬に直接接続する。ちなみに、嗅内皮質というのは、アルツハイマー病で最初に侵される脳領域の一つだ。
別の研究では、スーパーエイジャーの嗅内皮質にある全ての細胞層を調べ、ニューロンの大きさを丹念に測定した。その結果、情報伝達で最も重要な第2層において、スーパーエイジャーは大きく太く、無傷で美しい、巨大な嗅内皮質ニューロンを持っていることが分かった。
これは驚くべき発見だった。スーパーエイジャーの嗅内皮質ニューロンはもっと若い人たち、それこそ30代の若者より大きかったからだ。ここからうかがえるのは、構造的完全性という要素が関わっていること、つまり建築物のように、ニューロン自体の骨格や枠組みがより頑丈だということだ。
CNN:スーパーエイジャーの脳が損傷や病気、ストレスにどう反応するかについて、研究からどのようなことが分かっているのでしょうか?
ゲフェン氏:今はスーパーエイジャーの脳の炎症系を調べている。彼らの脳の免疫細胞が病気にどう反応し、ストレスにどう適応するかを理解することが目標だ。アルツハイマー病でも他の大概の神経変性疾患でも、炎症が一定のしきい値を超えると、細胞が失われる主因になる。
同年代の人の脳と比べ、スーパーエイジャーは白質内の活性化ミクログリア(脳に常在する免疫細胞)が少ない。白質は脳の高速道路で、脳内の一つの部位から別の部位へ情報を運ぶ役割を果たす。
仕組みはこうだ。ミクログリアは脳内に何らかの抗原や病気、通常は何か破壊的なものがあると活性化される。しかし一部のケースでは、ミクログリアなどの免疫細胞が過剰に活性化して暴走し、炎症、場合によっては損傷を引き起こしてしまうことがある。
しかし、スーパーエイジャーの脳では、活性化ミクログリアが少ない。実際、ミクログリアの水準は30代や40代、50代の人と同程度だった。スーパーエイジャーの脳内には不要物や病気が少ないため、ミクログリアが活性化する必要がないのかもしれない。あるいは、ミクログリアが効率的に対応して病気や毒素の除去を行うのかもしれない。スーパーエイジャーの脳は可塑性と適応力が高いことから、ミクログリアがいったん活性化して対応した後、鎮静化することが可能なのだろう。
どれも魅力的な説だ。もしかしたら細胞レベルで見た場合、スーパーエイジャーの脳の免疫系は嗅内皮質で見つかった細胞層と同様に、強靱性や適応力が高いのかもしれない。

英国では、「ノンドム(英国非永住者)」と呼ばれる国外出身の富裕層居住者に対する大規模な税制改革の導入後、億万長者やバイアウトファンド関係者、世襲資産家などの国外移住が加速している。
英政府は、英国国外の収入に課税しないというこれまでの制度を見直すことで、今後数年間で330億ポンド(約6兆5000億円)の増税効果を見込んでいる。だが、複数のシンクタンクがこの試算に異議を唱えており、雇用や経済成長への悪影響を警告している。
モナコやアラブ首長国連邦(UAE)といった低税率地域に移住する人が多い一方で、アルシャリフ氏のように母国へ戻るケースもある。ジャック&ジョーンズブランドを展開する衣料品大手ベストセラーの創業者トロールス・ホルク・ポウルセン氏も、最近になり居住地を母国デンマークに移した。ビール大手アンハイザー・ブッシュ(AB)インベブを創業した3大家族の一員でフレデリック・ド・メヴィウス氏も、母国ベルギーへ戻っている。

こうした上昇の背景には、大口投資家による暗号資産への関心の高まりがある。コインゲッコーの集計データによると、いわゆる「デジタル資産トレジャリー(DAT)」企業はこれまでに1130億ドル(約16兆6800億円)相当のビットコインを蓄積している。
BTCマーケッツの暗号資産アナリスト、レイチェル・ルーカス氏は「ビットコインが過去最高値に向けて上昇している背景には、トレジャリー企業や米国の現物上場投資信託(ETF)への継続的な機関投資家の資金流入のほか、米国による金地金への新たな関税措置を受けた市場心理の変化がある」と指摘。「金が供給面のボトルネックや政策リスクに直面する中で、ビットコインは関税の影響を受けない価値保存手段として、投資家の間で存在感を強めつつある」と述べた。


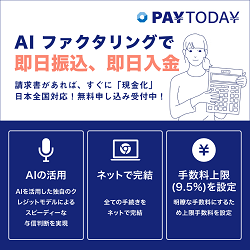

免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。



